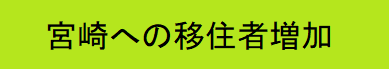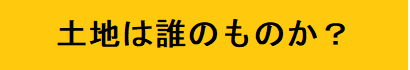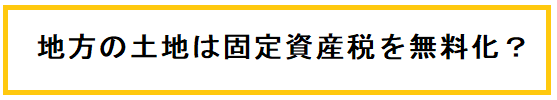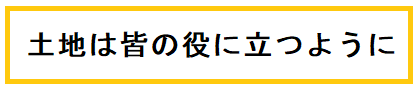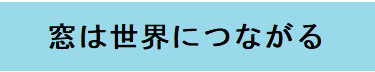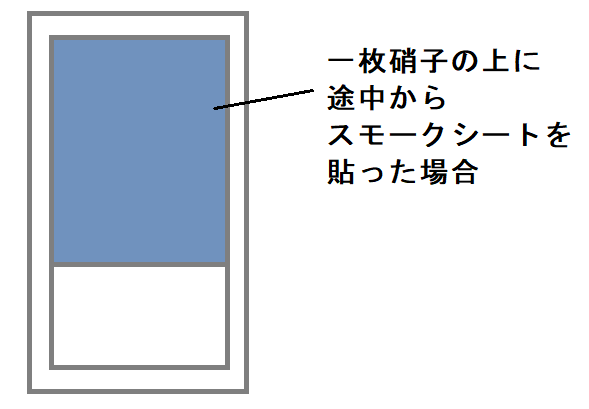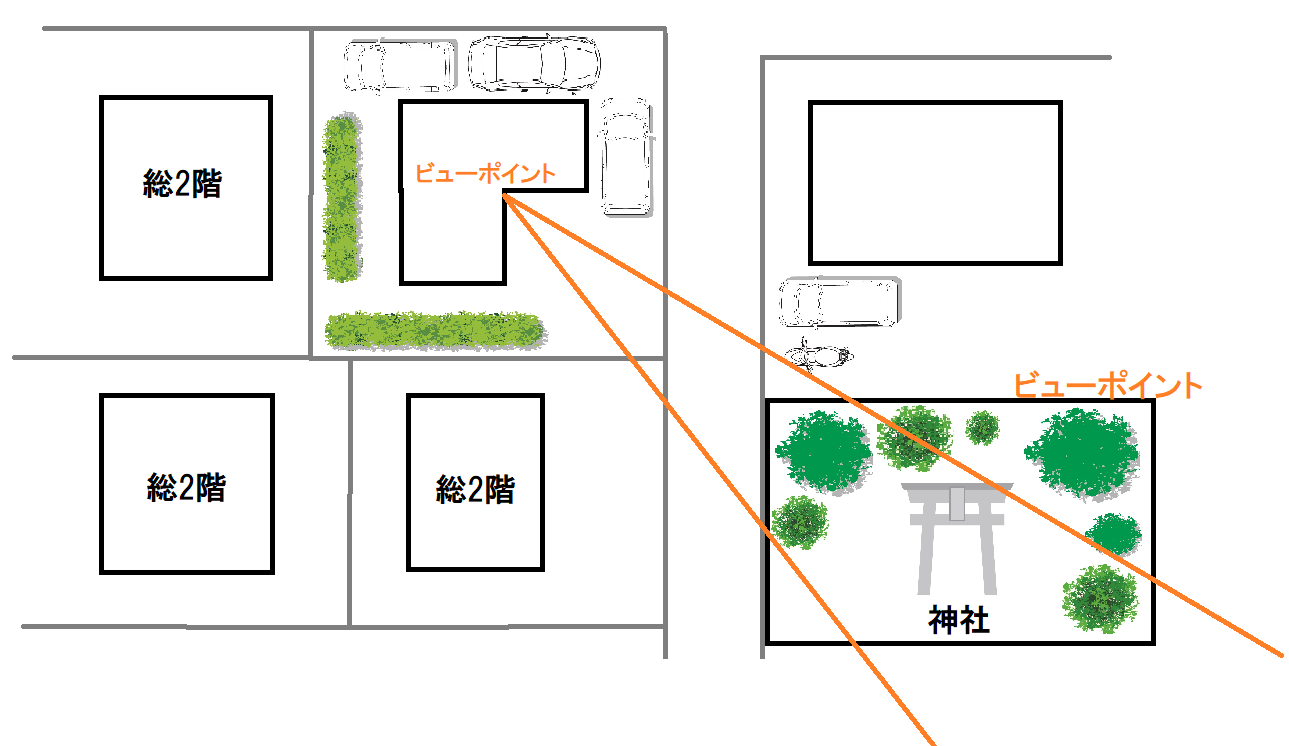子供にとっての宝は、たわいのないもの。
小学3年生だった私は、学生服で家族と並んで写真に写っている。父の転勤で引っ越しの折、駅のホームでの記念写真。見ると、上着の両ポケットはパンパンに膨らんでいる。おやっと、思ったが思い出した。
それは当時、お宝だった「カッタ」だった。
今の子供たちは「カッタ(鹿児島弁、メンコのこと)」と言われるもので遊ぶことはないが、鹿児島のそれは丸い形で子供の手の平ぐらいのもの。これを地面に打ちつけ相手のカッタをひっくり返すか、そのカッタの下に自分のカッタをすべり込ませたら勝ち。相手のカッタは自分のものとなるという遊びだ。
カッタには一枚一枚、その当時のヒーローが描かれていた。
マンガのヒーロー、赤胴鈴之助、ナショナルキッド、や野球の川上選手や大相撲の若の花、ゾウやライオンなど。
その日、箱いっぱいのお宝のカッタをポケットに詰め込めるだけパンパンになるまで詰めこんでいたのだ。
そうして、別れの列車に乗り込んだ。
煙もくもくのSLに。
住み慣れた故里「隼人」
懐かしい、優しかった人達、友達、遊んだ山や川。
生まれて初めて体験するSLは、もくもくの黒煙を盛大に吐きながら、霧島の長い長いトンネルにさしかかった。少しでも故里に近づきたいと、私は列車の最後尾に向かった。するとトンネルの向こうに空いた、明るい外の景色が、だんだん小さくなって、指で円をつくる程に。
その新しい街、高鍋では、四角いカッタが当り前で、鹿児島から持ってきた丸いカッタを誰も使ってはいなかった。
「お宝」は一瞬にして、価値を失った。
それはそれは、美事(見事)なまでに。
今、「僕」の両のポケットには、お宝は一つも入っていない。両手で掴み切れない丸いカッタを掴み取りポケットに詰め込めるだけ詰め込んだ、あの時を今更のように思い出す。
そうして心のポケットに大切な旅の伴侶を思い出した。
あの時、一匹の愛犬「チコちゃん」がリンゴ箱に入れられて同じ列車で鹿児島から宮崎高鍋に引越して来たことを。

小さくなった。
永遠に遠ざかる楽しかった思い出。
友達の顔、街がトンネルの向こうの明かりのように消えてゆくようだった。子供だった私は声をあげて泣いた。
その声を聞いて気遣って追って来た。父も母もおいおいと泣き出した。
あの時、泣いてくれた両親の姿に少し驚きながらも、ようやく「僕」は新しい街で生きる希望が持てたようだ。
これまで生きて来た瞬間のつながりの中で、何故か鮮明に見えて来る場面がある。
その「チコちゃん」を新しく引越して来た家の庭に繋いだ時のこと。
誰も知らない街で、一人と一匹の時間。
明るい冬の眼差しに照らされた竹やぶの景色がくっきりと見えて来る。
チコはそれから9年生きた。という訳で、今、私の心のポケットはチコちゃんだけでも満タンだということに、お宝満タンだということに気付いたという次第。
僕は、すばらしい家族をもっていたのだ。
チコちゃんも含めて。