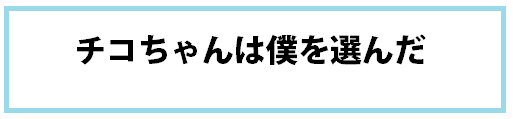転勤族の父に連れられ広島から、鹿児島県の集人町に移り住んでいた私は、ようやく小学校に通い始めたばかりでした。
昭和32年頃だと思います。テレビもスマホもない時代です。
兄弟の多い子ども達に比べ私は養子で「一人っ子」でしたので寂しい時を埋める何かを求める気持ちが強かったようでした。
とはいえ、当時の私にそんな自覚はあるはずもなく、そうして運命の日は突然やって来たのでした。
学校から帰ると誰もいない。どうしたのかとランドセルを置いて家の表に回ると、両親がいました。二人共しゃがみこんで何かを見ています。大きなバラの株元に一匹の小さな柴犬が繋がれていたのでした。名はチコちゃんでした。
「チコちゃん」に夢中になった小学1年生の私は、毎日学校が終わると一目散に自宅に帰りました。毎日どのようにチコと時間を過ごしていたか思い返してみるのですが、思い出せません。きっとうれしくて有頂天だったのでしょう。
出会ってから1週間程経った頃、勇んで家に帰ってみると「チコちゃん」がいません。不安になって両親を捜すと、あのバラの株の根元に繋がれていたロープだけがころがっていました。両親はそこに居ました。少し寂しそうな様子が気になりました。
「チコは、どこにいるの」
「チコはね、前飼っていた人が来て返してくれといって、連れて行ったよ」
「どっちにいった?」
「あっち」
その後は、一目散。家を駆け出して、幅2m程の用水路に架けられた板橋を渡り水路添いに東に向かって駆けに駆けた。どこまで走っても追いつけるはずもないのに。
でも、可愛そうな少年の為に、神様は奇跡を行われたのでした。
今を去る65年前物資の輸送手段は鉄道の貨車が全盛期の頃。その大量の荷物を運ぶ汽車はどれも車列が長く、それは延々と続いてしばしば踏み切り前には、足止めされた車や人が並んでいたものです。
そうです、奇跡とはこの長い長い踏み切り前の汽車通過前の車や人の列でした。
駆けに駆けた哀れな少年の目の前に見えて来たものは。なんと、チコはそこにいたのでした。
小型のバイクにくくり付けられた木箱に、お行儀よくちょこんとお座りしたチコ。
少年は呼びかけました。
「おい、チコ、帰るぞ!」
チコはポ~ンと木箱の底を蹴ると少年の元へ。
それからは、もう一目散にチコちゃんと少年は自宅まで逃げ帰りました。
チコはその日から14年少年の友として生きてくれたのでした。